

上記は、あっさり目の非乳化スープ
ベースは豚骨に、豚肉の出汁。
カラメの醤油と調味料、アブラで食わすタイプです
下の写真は、豚骨を長時間煮込んで、
白濁、クリーミーにした豚骨スープ
そもそもの二郎のスープではないタイプ?
ただこのタイプも、直系店で一度食べたことはあります。
個人的には好きなのですが、作るには手間がかかります。
豚骨の材料費と、ガス代がかかるので、
二郎インスパイア店でもこのタイプのお店は少数派?

( 3種類のスープを同時に作る )
スープを作る過程で火加減を調整しながら、
途中でスープを抜き取っていけば、
アッサリした非乳化スープ
やや白濁した微乳化スープ
濃厚なド乳化スープ
と、異なる味わいのスープを同時に作ることも
可能だと思います。

左: 自作
二郎風オーション極太麺 (300g)
(オーション、塩、水 、 かん水)
右: 市販の中華麺 (140g)
(小麦粉、澱粉、小麦たん白、食塩、酒精、
かんすい、乳酸Na、クチナシ色素)
< 麺 >
小麦粉+塩+かん水+水 などで作りますが、かん水がない時は食用可の「重曹」で代用できます。
二郎は塩は入れないんでしたっけ・・?
二郎のような極太麺は手打ちでも作ることができます。
手打ちの場合は、練り水( 塩+かん水+水
)の合計量は、小麦粉に対して40〜45%くらいにします。
水分量が多いと、モチモチした食感になりやすいですが、
手打ちの場合は、水分量を多くしないと作れません。
詳しい作り方は「手打ちうどん」で検索すると良いと思います。
簡単に作る場合は、
・ 小麦粉と練り水を、ムラなく混ぜる
・ よくこねてから団子状にして、乾燥しないよう袋に入れて
最低30分以上は寝かせる
・ その後、麺棒で延ばして生地にする
・ 打ち粉(片栗粉・コーンスターチでOK)を振った生地を
折りたたみ、包丁でカットして出来上がり
麺は茹でると少し太くなるので、希望のサイズより少し細く切っておきます。
( 分量 )
200gの小麦粉なら、加水率40%だと練り水は80g。茹で前、280gの麺が作れます。(加水率45%なら練り水は90g)
※45%のほうが生地が柔らかく、力がなくても作りやすい
ですが、麺のモチモチ感は強くなります。
※玉子を入れる場合、玉子は練り水の重量に含めます
パスタマシンがある時は、加水率は35%前後でいけると思います。 (パスタマシンでの自家製麺は コチラ)
かん水と塩の分量は、練り水に対して、それぞれ3%くらいの濃度にするのが一般的なようですです。
(分量に決まりはありません。お店や製麺所が作る麺も、麺の種類や季節・天候などによって、割合を変えています)
ラーメン二郎を真似る場合は、小麦粉は オーションを買うのがベストですが、なければ普通の「強力粉」でもいいと思います。
うどん用の中力粉は、もっちりした食感になるので、ゴワゴワ麺を作りたい時には向きません。
国産の強力粉も中力粉寄りの特性なので、
もっちりツヤツヤの麺に仕上がると思います。
なので、ゴワゴワ・ワシワシの麺を作りたい時は、外国産の強力粉を選びます(普通スーパーに売っているのがそうです)
手打ちうどんの太さですと、ゆで時間は7分以上、味見しながら、引き上げるタイミングを見計らうことになります。
なるべく失敗しないようにするには、
最初に数本だけ茹でて試食し、ゆで時間を確認してから、
本番茹でをすると良いと思います。
< ヤサイ >
直系の二郎のお店って、モヤシは10秒くらいしか茹でないこともありますね、 キャベツを入れて1分〜 経った後に、モヤシを入れて、すぐ引き上げる。
一方、インスパイア系のお店では、何分も茹でているお店があります。
モヤシは、10秒くらいが一番シャキシャキするそうです。
クタっとしたモヤシが好きな方は、長めで良いと思います。
たまに、インスパイア系のお店で、モヤシが臭うことがありますが、茹で湯が真っ茶色になってるのでは・・
茹で湯の臭いは、モヤシの生臭さとは違うんですよね。
モヤシは、メーカーによって太さがマチマチですので、少し太くて、しっかりしたモヤシのほうが良いかもしれません。
業務用のモヤシは、安いのでだいたい1kg100円、4kg入りで400円くらいだと思います。(通常は1kg125円くらい)
二郎ではいくらモヤシを大量消費するといっても、モヤシ屋さんはモヤシを売っても大して儲からないので、それほど値引きはないかもしれませんね。
となると、野菜マシ・マシマシ(軽く700g以上はある?)の
原価は、バカになりませんね。 ヤサイ少な目のお客さんもいるので、バランスは取れるのでしょうが。
※ ネットではモヤシ4Kg袋を200円代で購入したという記事も見かけますが、常にその値段で買えるものなのかどうか・・? 私には分かりません。ちゃんと消費期限が2〜3日あるものが200円代で買えたのかな・・・
< ニンニク >
にんにくは、種類や時期によっては、刻んだり、すり下ろしたりすると、緑色に変色することがあります。
焼肉屋さんでも、肉の下味に付いているニンニクが緑色になっていて、肉の見た目が悪くなっていることがたまにあります。
ただ、緑色になっていても、食べるのは問題ないそうです。
万が一変色すると、見た目が悪いので、ニンニクは刻んだら、変色しないうちに食べるのがベストですね。
生のニンニクは、食べ過ぎると胃腸に負担がかかるそうです。1〜2粒分くらいがいいみたいです。
人気繁盛店「ちばき屋」のレシピDVD
業界初!『
らーめん屋開業・運営・経営・支援 』
移動販売・屋台に役立つ話
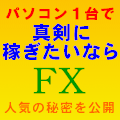
|
< スープを作る >
※ラーメンを初めて作る方は、こちら もご覧下さい。( 材料 )
豚骨(ゲンコツ又は背ガラ、アバラ骨等)、豚肉、背 脂、
香味野菜
(キャベツの芯・ニンニク・ねぎ・人参・タマネギ・ショウガ等)
※ 野菜臭くならない程度に適量
家庭では通常、
一度に材料を全部入れてスープを炊き出すと思いますが、
一度スープを作って、一晩寝かせてから、さらに翌日新しいガラや豚肉を追加して煮込む方法でも面白いと思います。
スープの味に、どういった違いが出るのか・・な?
興味があるところです。
または、スープは少し多目に作っておき、残ったスープは冷凍して、次にスープを作る際のベーススープとして加えても良いかもしれません。
一人前あたりの参考分量 (完成時スープ 400cc
前後 )
スープの豚骨濃度が薄い、ライト系
非乳化スープ
・ 豚骨(ゲンコツ又は背ガラ等) 200g〜300g以上
・ 豚肉 300g 以上
・ 背脂 100g 〜 ( トッピング分も込み )
スープの豚骨濃度が高い、非乳化、または微乳化スープ
・ 豚骨(ゲンコツ又は背ガラ等) 300g〜400g以上
・ 豚肉 300g 以上
・ 背脂 100g 〜
白濁してクリーミーでコクがある、乳化系スープ
・ 豚骨(ゲンコツ又は背ガラ等) 400〜600g以上
・ 豚肉 300g 以上
・ 背脂 150g〜
・ ( ドロドロ、トロトロにしたい場合は、豚足も追加 )
※ アバラ骨(込みガラ)などを混ぜても可
( トンコツの下処理方法 )
鍋にお湯を沸騰させ、
ゲンコツは15〜30分、背ガラは15分程度下茹でし、
血抜き、灰汁抜きをします。
その後、流水で骨に残った血合いを洗い流し、アクの塊が
付いている場合も洗い流します。
下茹でしたお湯は、捨てます。
ゲンコツは白骨の中の骨髄を露出させるために割ります。
片手でゲンコツの端を持ち、白骨の真ん中をハンマーで叩いて半分に割ります。 鈍く重い手応えの場所は割れないので、軽い手応えの場所を叩くと割れます。(
ケガに注意 )
骨髄から出汁が出やすくなれば良いので、ドリルなどで穴を開けても構いません。
背ガラは鍋に入る場合はそのまま煮込んで大丈夫です。
少し細かく割ってしまっても構いません。

ハンマーで割った後の、ゲンコツの写真。
真ん中の白骨の中に見えるのがダシの元となる骨髄です。
( スープの作り方 )
下処理した豚骨と背脂、野菜を鍋に入れ、水から煮出します。 豚肉はお湯が沸いてから入れたほうが旨味の流出は少ないかもしれません。 肉そのものの旨味は減っても、スープに豚肉の旨味を多く移したい時は、最初の水の状態から煮込んでも良いと思います。
最初のうちは、まだ少し汚れたアクが浮いてくるので、
その都度、すくい取って捨てます。
豚骨や豚肉は、鍋の底にひっついてないか、確認します。
材料が鍋底にくっつくと、焦げの原因となり、焦げ付かせるとその時点でスープ作りは失敗に終わります。
非乳化系(透明〜茶濁)スープの場合は、トンコツを弱火〜中火で最低
3〜4時間煮込めば良いと思います。
ゲンコツの場合は、8時間程度まではダシが取れますので、希望のスープ濃度になるまで煮込めばOKです。
乳化系(白濁)スープの場合は、豚骨の量を増やして8時間以上、中火〜強火で煮込みます。モミジ(鶏足)や豚足、豚皮などゼラチン質の多い材料を加えると、粘度が増してトロトロのスープになります。
長時間煮込む場合は、トッピング用の背脂は2〜3時間経って柔らかくなった段階で、取り出します。
豚肉は部位や大きさによって適切な煮込み時間は変わりますが、1〜3時間で取り出します。(
下記参照 )
豚骨は鶏ガラと違い、少量煮出しても、それ程美味しい味がするスープにはなりません。
豚肉を加えるので、豚肉から出る旨味は感じやすいと思いますが、通常の材料の分量ですと、スープ自体は思ったより味がしないかもしれません。
カエシ(タレ)と、化学調味料を入れれば、ちゃんとスープの味にはなるので大丈夫です。
< ブタを作る >
豚肉はウデ肉(肩肉)があればベストですが、入手できない場合は肩ロースやモモ肉、又はバラ肉で代用します。左写真の肉は、肩とバラの間にある肩バラ肉(脂身が多い)です。
豚肉もトンコツと一緒に、スープで煮込み出汁を取りますが、
ウデ肉やモモ肉、肩ロース肉は脂身が少なく、長時間煮込み過ぎると、パサパサになってしまいます。肉の塊の大きさにもよりますが、1〜2時間 経ったら、スープから引き上げます。
バラ肉や肩バラ肉は脂身が多いので、2〜3時間程度煮込めば、トロトロのブタが出来上がります。
バラ肉などは長時間煮込むと、赤身と脂身が分離してしまうので、タコ糸で縛るか、ネットに入れて煮込みます。
→ 煮込んだ後、熱いうちにタコ糸をほどくと分離してしまうので、いったん冷まして、肉を少し引き締めてから、たこ糸をほどきます。
( 豚肉のゆで加減を確認する )
豚肉に火が通っている場合、串を刺すと、透明な汁が出てきます。赤い汁が出てくる場合は、まだ完全に火が通っていません。(串は数カ所に刺して、確認します)
串が抵抗なくスッとスムーズに入れば、ホロホロとしたブタになっているので、パサつく前に取り出します。
反対に、串がググっと引っかかって入る時は、まだ煮込みが足りないか、または、煮込み失敗で、すでにパサパサになっています。
※脂身の少ないウデ肉(カタ肉)・モモ肉を柔らかくホロホロに作るのは、なかなか難しいです。同じ部位の肉でも、切り出された場所によって脂のりが異なるので、脂がのった肉を選ぶと良いと思います。
反対に、バラ肉の場合は、脂が多すぎない肉を選びます。
試したことはないのですが、バラ肉の脂が多い部分とウデ肉を混ぜて、タコ糸で縛って煮込んだら、どうなるのでしょう?
神ブタになるのかな・・?
( 肉同士は、冷やせばくっつきます )
( ブタの味付け )
スープで豚肉を煮込んだら、取り出して熱い状態のまま、
カエシ(醤油ダレ)に20分程度、漬け込みます。
※直系7〜8cmの肉の場合。 肉が小さい時は、しょっぱくなるので、もっと短時間でOKです。
豚肉は熱い状態だと切りにくいので、少し冷ましたほうがカットし易くなります。
< カエシを作る、グルを入れる >
濃口醤油 + 薄口醤油、みりん風調味料
(又は、本みりん)
→ スープで煮たブタを漬け込んで完成
化学調味料 (味の素など)
二郎系はカエシ(醤油ダレ)を普通のラーメン(30cc程度)の2〜3倍入れると思うので、濃口醤油だけでは色が濃くなり過ぎます。
こいくち醤油の持つ旨味も欲しいですし、うすくち醤油と半々の割合で調合すればいいかもしれません。
カネシ醤油が手に入らない以上、想像の範囲で皆さん作っているんじゃないかと。 カネシを使っているお店の方が言うには、「普通の醤油と変わらないよ」とのことでしたが。
みりん風調味料(または、本みりん)の量も、店によって甘味が違うので、あくまで好みでしょうか。個人的には富士丸系は甘過ぎて苦手・・ 2店しか知りませんが。
二郎の店員さんも、「甘いのはみりんが多いからじゃない?」っと言ってましたが、野菜から出る甘味も含まれてるんですかね・・謎。 ラーメン大(堀切系)はスープに野菜の匂いが強い感じがしますが、甘くないし・・
本みりんを使う時は、一度加熱して、アルコールを飛ばします。鍋で加熱し、チャッカマン等の火を当てて燃えなければ、大丈夫です。家庭では炎が出るほどの量は使わないかもしれませんが。
ニオイを嗅いで、アルコール臭くなければ大丈夫だと思います。
「みりん風調味料」 は、加熱しなくてもそのまま使えます。
「 醤油 」
は、加熱するかしないかは、好みだと思います。
加熱する場合は、焦げないよう85℃くらいまで加熱すれば大丈夫です。
醤油とみりん風調味料を混ぜたら(加熱したら)、
スープで煮込んだブタを漬け込み、肉の旨味・風味を
移して完成です。
スープと合わせるカエシの分量は、好みの問題もありますし、
モヤシの量などによっても、適切な量は変わってきますので、
その都度、調整すれば良いと思います。
そういえば某インスパイア店でヤサイマシをせずに食べたら、
頭が痛くなるほど、ショッパかったことがあります。
今まで食べたラーメンの中で、一番しょっぱっかったです。
スープを足してもらおうかと悩みましたが、スープマシなんて
聞いたことないですし、仕方ないので我慢して食べました・・・
化学調味料は、グルエースが使われていると言われていますが、実は、グルタミン酸ソーダだという噂もあります。
どっちも、似たようなものだと思いますが。
スープに入れる分量は、お好みですね。
味の素やグルエースではなく、「ハイミー」や「いの一番」などを使う場合は、旨味が強いので、1/2
〜 1/3 くらいの量でOKです。
ハイミーなど複合系のうま味調味料は、使用する量は少なくて済みますが、その分、値段も高いです。
< アブラ : 背脂トッピング>
背 脂にはグレードがあって、A・B・C脂などと呼ばれます。
上質なのはA脂です。たまに量販店で分厚い背脂を買うと、臭くてたまらん時があります。
ロース部分から
そぎ取ったような比較的薄めの背脂を選ぶと良いと思います。
背脂は、豚の首筋に近い部分から取ったモノは、筋のようなモノが入っており、お湯にはなかなか溶けきらないそうです。
確かに、たまに量販店で買って来る背脂の中には、筋というか固いモノが中に入っていて、溶けない箇所があります。
ロース肉の真上ではなく、前のほうから取った背脂は、そんな感じで混ざりモノがあるのかもしれません。
トッピングに使用する豚背脂は、
スープ材料と一緒に煮込んで、2〜3時間経って柔らかくなったら鍋から取り出し、網で濾したり、ハシでグジュグジュと混ぜて潰したり、包丁で小さくカットしたりします。
食べる際にスープに浮かべたり、ヤサイの上にのっけて食べます。 醤油ダレなどで味付けをしても良いと思います。


|